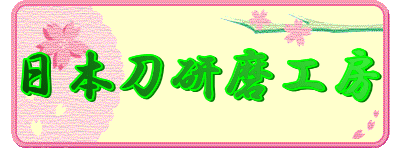top > 研磨実演

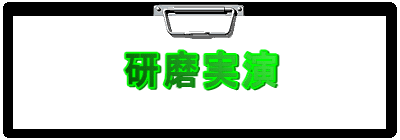
|
このページは以前ご紹介しておりました”研磨の実際”のリニューアル版です。 ”研磨の実際”を掲載している時も全国から「大変参考になる」、「次の工程が楽しみ!」等たくさんの励ましのメール、ご意見ご感想をいただきました。 内容的にも前回説明不足だった事、お伝えしきれなかったことも御紹介していきたいと考えております。
(ページの下から上に御覧ください)
ご意見ご感想などもお寄せください。
|
|
研磨を終えて・・・
|



研磨工程の全てを終え本日、やっと仕上がりました!見るも無残な状態で白鞘もハバキもない状態だったこの脇差に本来の光が蘇りました。
腰反りの姿も整い、弱い地金と比較的綺麗な地金が混在する肌、砂流しも輝く互目の刃紋も鑑賞に堪えられるものになりました。
正直言ってこのページでご紹介していくにはちょっと不安もあり、「最後まで続くかな?」と思ったりもしましたが、こうして仕上がった脇差を見ながら嬉しくもありホッとしています。
休日やお客様からの御刀の合間に行ってきましたから、時には疲れから投げ出したくなる時もありました。
また、写真撮影が上手く行かず、ピンボケや照明不備でそちらにも多くの時間がかかり過ぎた事もありましたが今となっては良い経験だと思っております。
結果的には決して名刀ではありませんでしたがが手をかけるほどそれに応えてくれるというしぶとさを持った脇差でしたね。
そして、当初はただの錆脇差程度にしか思わなかったこの脇差ですが研磨工程が進みながら段々愛着も出て来て好きになりました。
まさに私にとっての”愛刀”といった感じです。
当工房には様々な御刀が研磨御依頼で送られてきます。そして様々な思い入れを持たれたお客様からのメールもいただきます。
私がこの脇差を研磨しながら抱いた愛着をお客様各位も御愛蔵の御刀にお持ちだという事を改めて感じることも出来ました。
”研磨実演”というこのページがきっかけで自分所有の脇差を研ぐ事になり、お客様の立場に立って研ぐことの大切さも再認識する良い機会になったと思っております。
今後も今まで以上にお客様の御刀への思い入れや愛着心を感じながら研磨させていただきたく思っております。
この脇差からもいろいろ学ばせてもらいましたので感謝です。
最後になりますが研磨完了まで御覧頂き、本当にありがとうございました!
|
ナルメ
|



いよいよ研磨の最終工程である帽子ナルメまで来ました。
ナルメとは切っ先の部分を刃艶で研磨する、切っ先部分の最終研磨です。
はじめに横手下の研磨済みの部分は全て越前奉書紙を巻き、丁寧に保護します。
それから”筋切り”といって横手の線を切ります。
この際には横手板という竹製の板を横手に当て、それに沿って刃艶を動かしますと横手の線がくっきり入ります。ただし、横手と言うのは下地の段階で既に正確に立ててありますから下地の横手からずれると色ムラが出てしまうので慎重に、正確に筋切りを行います。
筋切りを終えたらナルメ台(右の写真)という木製の台に和紙と上質の刃艶を置き、切っ先内を”切”つまり刀身と直角方向に研いで行きます。
ナルメ台は朴の木製で御覧のように鋸で切れ目を入れて弾力が付くようになっています。
このナルメも下ナルメと上ナルメに分けて行い、ナルメ台も弾力の弱いものから強いものまで用意しております。
刃艶もナルメ用は特別に選別して最適なものを用意するのは勿論ですが、その厚さも刃取り以上にシビアになってきます。
さて、この脇差のナルメも御覧のように均一な美しい白さに仕上がりホッとしてます。
切っ先は人間で言えば顔です。
刃取りや磨きが上手くいってもこのナルメが成功しませんと非常に見苦しくなります。
逆にこのナルメがうまくいきますと格段に見栄えしますから最も大事な工程とも言えますね。
ナルメが終えてから、補足的に小鎬の際だけ上磨きを軽くしましてナルメの工程を終えます。
これでこの脇差の研磨が終わりました。
次回、この脇差の研磨を振り返って総合的な感想など述べてみたいと思っております。
|
上磨き(あげみがき)
|



磨きの工程は上磨きまで完了しました。
上磨きとは、下磨きでの磨きムラを細かく修正しながら磨き面を最も細かい目にし、同時に芯から黒く半鏡面状態に磨き晴らす作業です。
画像では前回の下磨きと大して変わらない色合いに写ってしまい(写真撮影が下手なので御容赦ください)残念ですが、実際の作業では全く違う黒い色合いになってきます。
使う道具は磨き棒ですが、磨き棒自体の表面研磨が下磨きのそれとは全く違います。
また、下磨きの際はほとんど一本のヘラで間に合いますが、上磨きでは刀身の硬さや鍛えの粗密に合わせ様々な形状、太さのものを用意し、御刀に最適と思われる磨き棒で仕上げていきます。
磨く幅は約2cmずつ、最も気を使うのは、鎬地や棟の鍛え肌を潰しすぎないようにすることです。
この脇差のように大肌が柾目に流れているような場合はまだ良いのですが、詰んだ地金の場合はややもすると鍛えが全く見られない、即ちメッキをしたような品のない仕上がりになりがちです。
古刀では美濃伝、その美濃伝の影響を受けている新刀全般の鎬地は柾目の鍛えですからそれが分からなくなるまで潰してしまうのでは磨きの意味がありません。
では何故、美濃伝や新刀は鎬地が柾目になるかというと造り込みが”甲伏造り”だからだと思います。
分かりやすくする為に自分の右手掌に二つ折にした厚めの雑誌を挟むようにしてみますと、見開き側にページの紙の層が出来ますね。自分の右手が芯金、雑誌が皮金、ページの層が鎬地に現れた柾目肌というわけです。
本題に戻りますが、昔は今のように超硬の磨き棒がありませんでしたから、鋼の棒に焼きを入れたもので磨いていたそうです。
イボタで滑りを良くするとは言っても、鋼同士を擦るわけですから使用しているうちにナマってしまい、度々焼き入れをしながら磨いたそうです。
それにしても、いつ頃からこの磨きという作業を行うようになったのか正確にはわかりませんが、考え出した先人は凄いと思います。
下磨きの項でも書きましたが、磨くことによって刃の白さは一層際立って見えますし、また、地金の青黒さとは違う金属光沢が刀身に美観を添えます。
下地研磨では平地の肉置きという曲面と鎬地、棟の平面の対照、仕上げ研磨では刃取りの白さと磨きの黒さの対照が見事に調和して日本刀美を形成していることに気付きます。
さて、次回はナルメの工程をお伝えしたいと思います。
|
下磨き
|



下磨きという工程です。
”磨き”とは鎬地と棟に金属光沢を付ける作業で通常は下磨きと上磨きに分けて行います。
鎬地、棟の鍛え肌をある程度は潰しながら黒く磨くのが下磨きの目的です。
下磨きの道具は砥石ではなく右の写真のような磨きヘラや磨き棒です。
材質はタンガロイという超硬の合金で出来ております。ダイヤモンドの次に硬質なものですから鎬地の表面を磨くには最高です。
実際の作業としては刀身の油分を完全に除去してから打ち粉、イボタを打ち、静かに磨いていきます。
ちょっとでも油分がありますと磨けないだけでなく”トッツキ”という白い筋が立ちますので注意しながらの作業です。
また、超硬のためすぐに金属光沢が付き能率は良いのですが、裏を返せば金属疲労を起こさせやすいという面もあるわけで、できるだけ最小の圧力で、同じ箇所を磨き過ぎないという配慮も考えて行います前述のイボタとはヘラの滑りを良くする粉で、カイガラムシという虫の分泌物を粉末にしたもの、成分は蝋分です。
右の写真のヘラや棒に撮影用に”上”や”下”と書いておきましたが”上”と記入してあるヘラはヘラだけで上磨きを行う場合(主に格安研磨の際)に使っています。
”下”と書いてある棒は小鎬地や区際などの微妙な箇所、ヘラではやりずらい箇所を下磨きする場合に使います。
さて、下磨きを終えますと磨いた鎬地の黒さの影響で前回の刃取りの白さもより強調されて美観もますます増してきます。
刃の白さ、地金の青黒さ、鎬地の金属光沢の黒さという色合いの違いが日本刀の美を形成しているという事がご理解いただけると思います。
さて、下磨きで大体の金属光沢が付きましたが、このままではヘラの磨き跡や色ムラもまだ少しありますし、磨いた面も粗いですから最終的な磨きは次回の上磨きで調整していきます。
次回は上磨きをお送りします。
どうぞお楽しみに・・・。
|
刃取り(後刃拾い)
|



金肌での拭いを終えた刀身は刃の中まで青黒く拭いが入ってしまいますので、ここで”刃取り”という作業を行います。
刃取りの手順としては、刃の輪郭を拾う”下刃”、刃中を均一な砥目に均す”ならし”、刃縁を地に煙りこむようにボカす”ボカシ”という作業に分類されます。
使う艶は下刃艶と同じ内曇を薄く割って和紙を裏張りしたものですが、下刃艶時以上に良質の砥石を吟味して刃取りに用います。
同じ刃艶を使うとは言っても、内曇刃引砥の粗い目を除去するのが目的の下刃艶と、既に細かい肌理になっている砥目の上から改めて白く修正していくこの”刃取り”という作業が全く違う工程であることは想像に難くないと思います。 即ち、形状は刃の山に合うように小判型若しくは楕円形にした、下刃艶よりもかなり薄くした刃取り専用のものを用います。
刃紋の通りに拾うのが原則ですが刃縁に沸えが付いているこの脇差の場合などはある程度地にも突っ込んでいかないと刃の白さと働きを表現できませんからそのライン取りも研師の腕の見せ所とも言えますね。
しかし、ただ白くすれば良いというのは大きな間違いです。
濃厚な砥汁を使えばたちまち白くなりますが、刃中の働きも鍛えも全く見えない状態になります。
これでは何の為に刃を白くするのか意味がありませんから、本当に刃の中の芯から砥石が効くまで時間をかけてこなしていきます。
刃取りのライン取りとも言える”下刃”が完了したら、刃中の砥目を最も細かく、しかも働きも充分に表現できるように極薄くなった艶で均します。
一定の力加減と動かすストロークも調整しながらの根気を要する作業ですが、同時に白く輝きを放つ刃紋が出来てくると本当に綺麗だなと感じます。
最後に”ボカシ”です。
裏張りした和紙が見えるか見えないかほどに薄くなった艶で刃縁をボカして自然な雰囲気を表現します。
ただ、このボカシは一番の難関で、お客様によってはキッパリとした刃取りでボカさないほうがお好みの方もおられますから微妙ですね。
さて、これで平地に関しては概ね完成しました。
次回は磨き(下磨き)を行います。ご期待ください。!
|
金肌拭い
|



金肌拭いに入りました。
金肌とは刀匠が火作りの時にできる酸化皮膜のことでいわゆる酸化第二鉄です。
この金肌を炭火でじっくり焼いた後、乳鉢で微粉末になるまで磨ったものを椿油などで溶いたものです。
実際に使用するに当っては吉野紙数枚で濾し、刀身に置きながら綿で磨くという作業です。
当工房では金肌自体も刀匠さんから分けてもらったもの、一般の鍛冶屋さんから分けてもらったもの、自家製の金肌という具合に金肌も使い分けて、その焼く時間もデーターをとって最も相応しい金肌を使用しております。
金肌拭いを入れる前には勿論それ以前の地艶は充分適切に処理されているか、思わぬヒケが入ってないか再三確認した上で拭いを開始します。
何故なら、拭いを入れてからではもはや後戻りは困難です。
今までの研磨は水をつかって砥石で磨く作業でしたからある程度やり直しも可能です。
しかし金肌拭いは酸化鉄という硬い粒子の粉末で油を媒介に刀身面を潰しながら光沢を出すという作業内容であることから誤魔化しも一切効きません。
刀によっては地艶は最高に美しかったのに拭いを入れたらバサバサになった、なんていうことも今まで幾度と無く経験してきました。
ですから金肌拭いを入れる前はかなり緊張します。
幸い今回の脇差は色合いも肌も理想的に上がり満足してます。
差込研磨の場合は金肌ではなく磁鉄鉱を主体に対馬砥粉末や辰砂(硫化水銀)などを混ぜて用います。
磁鉄鉱は四三酸化鉄で、同じ酸化鉄ですが効きが遅いので硬い刃部が結果として白く残り、柔らかい地は黒く拭いが入るというわけです。
いずれにしましても拭いはあまり長時間続けると地金が焼けてきたり、バサバサになりますから、短時間で済ませることが肝心です。
右の写真は当工房で使ってる拭いです。
御覧のように油で溶いたペースト状の金肌を容器に入れて保管、使用の際は舟形に作った吉野紙で刀身に置き、綿で磨きます。
この綿も単に市販のものをそのまま使うのではなく丸め方や厚さ、硬さなども考慮して作ります。
金肌拭いでも差込拭いでもありきたりの方法ではなく、お客様の御刀に最も相応しい最良の方法は何か、いつも考えています。そしてそれがピタリ当ったときは本当に嬉しくなります。
拭いを終えた刀身は刃中も青黒く染まりましたから次回、後刃を拾って行く予定です。
ご期待ください。
|
地艶
|



仕上げ研磨においてのメインイベントと言える地艶に着手しました。
この工程は仕上げにおいて本当に気を使いますし、デリケートな工程なんです。
はじめに下地艶と言って内曇の砥目を抜く為に軟らかい合砥(京都産出天然砥)のコッパを薄く割り砕いた”砕き艶”をかけていきます。
合砥は軟らかい地艶ですから肌が伏さらないように注意しながら内曇地引の目を丁寧に抜いていきます。
次に更に硬質の本山鳴滝砥を薄く(0.2mmくらいでしょうか)に磨ったものを同じく砕いて地金を晴らして肌や働きを目に見える形にしながら砥目も最も細かくしていきます。
一般的には硬い地金には軟らかい艶、軟らかい地金には硬い艶という原則がありますが、
地艶だけは本当に難しく、やってみないと地金に合うかどうか未知数の要素がありますね。 数年前、京都のいろいろな仕上げ砥石のコッパを集めて試した事もあります。
即ち、車口や菖蒲谷、戸前、というブランドの他、山別に大平山、大突山、中山、音羽山、マルカ等色々試して良いものは採用し、現在に至ってます。
本当に地金と合うと真っ黒い砥汁のみ出て地金も晴れて美しくなるのですがそれを探すまでが毎回大変です。
時には合う砥石を探すだけで2,3日かかることもしばしばですが当工房に御依頼してくださったお客様の為には妥協はできませんね。
さて、左の写真は地艶をかけ終えた写真です。
肌の出具合、色合いもほぼ満足いく感じです。
中央は艶を乗せた写真です。
当工房では”砕き地艶”を主体に地艶をかけますが、張り艶も(右の艶)も使います。
両者一長一短ありますからその都度使い分けての作業です。
私が研磨の指導を最初に受けたのは張艶でした。
研磨研修会で砕きを指導された時は正直驚きの連続。
それ以来、10年以上経ちますが、扱いなれている張り艶、そして砕き艶の両方を刀身に
応じてなんとなくですが使い分けられるようになりました。
これは御依頼下さるお客様のおかげだと痛切に感じてます。
さて、プロではないアマチュアの一般愛刀家の方が研磨にチャレンジなされて一番の難所が
この地艶だと思います。これを期に「到底研磨は無理だ」と思われた方もいるはず。
ヒケだらけになってしまうし付いたヒケは何としても取れない、そんな方もいますよね。
刃艶まではかなり軟らかい艶ですから良いのですが地艶は相当硬い砥質ですからヒケも付きやすいものです。逆にヒケが付きやすいくらい硬質な砥石でないと地金の妙が発揮できない刀も実際ございますから大変です・。
この脇差もやはり差込研磨には向かない感じですので通常の後刃拾いの仕上げを行うことにいたしました。
残念ですが御了承ください。機会がありましたら差込に向く作品を見つけてご紹介したいと思います。
当工房のホームページでは研磨ご依頼のお客様だけでなく刀剣全般に関するお問い合わせもいただきたく存じます。
日本刀を通しての繋がり、交友を深めたいですね。
次回は拭いを行います。
|
下刃艶
|



今日から仕上げの工程に入りました。
刃艶は内曇砥のコッパを薄く割ってから平らにして、和紙を裏張りしたもので行います。
厚さで言うと0.5mmくらいでしょうか、とにかく薄く紙のようになったもので刃の中を磨いていきます。
左の写真は刃艶をかけた状態とそれに使う刃艶です(中央の四角い茶色のもの)。
刃艶をかけていくと写真のように次第に白くなってきて刃縁の沸や働きも鮮明に見えてきます。
地の方にもある程度突っ込まないと刃縁が冴えないのですが、あまり地に強くかけてしまうと
せっかく地引きで出した肌や冴えも無になりますから、初めは刃中に良く効かせて薄くなってから刃縁や刃先に用いております。
中央の写真は刃艶をかけ終えた刀身の写真、右の写真は今回用いた裏張りして作った刃艶です。
刃艶の目的は下地での内曇の砥目を充分に均しながら砥目を細かくし、同時に刃の艶や冴え、働きを顕現できる状態にもっていくことです。
刃艶をかけると、いよいよ完成も近いなと思えてきて毎回ながら気合も入りますし、楽しくなってきます。
早く仕上げたいという逸る気持ちを抑えつつ丁寧に刃艶をかけてみました。
次回は”地艶”をお送りします。
|
内曇砥地引
|



内曇砥を充分に効かせ、細名倉の砥目も完全に抜けましたら、地と鎬地、棟をさらに硬めの内曇砥で引きます。
これを内曇地引と言います。
軟らかめの内曇の砥目の奥に沈んでいた細かい肌まではっきりと表面に現れてくるようにする工程です。
例えていいますと白い靄を晴らしてくっきりさせると言う感じです。
この脇差は大肌の部分、弱い金の部分、詰んでしっかりした部分と言う風にところどころで地金が違いますから、その箇所ごとに引き方を変えたり、硬さの異なる内曇地砥を当ててみたりする必要がありました。
この工程で出すべき肌は充分に、そして抑えなければならない弱い部分は滑らかにと言う具合に地金を揃えておくことによって仕上がりがかなり違ってきますから重要な作業です。
できるだけ短めに引きながら細かい肌を起こすように、しかし肌を裂いたりしないように注意して次の仕上げ研磨の事もイメージしながら行いました。
ほぼ満足いく肌合いになり内曇砥の最も細かい砥目も美しく輝いています。
これで砥台で研ぐ下地の工程は終了です。
余談ですが、このページに載せる写真は3枚ですが20枚以上撮ってその中からその工程の砥目、
肌や刃紋の映りが良く分かるものを載せています。
写真の撮り方が下手なのは御容赦いただくとして、写真と言うのは研磨中には見落としてしまった
細かい研磨不十分な箇所なども鮮明に写すものだとつくづく思いました。
ですから撮影後に再度やり直し、改めて撮影ということもありました。
これはこれで大変有意義で、勉強になりますね。
さて次回から仕上げの工程に入ります。
お楽しみに・・・。
|
内曇砥
|



内曇砥に入りました。
この内曇砥は細名倉の砥目を除くと同時に仕上げ研磨につなげる橋渡しともいえる工程です。
研師さんによってはここからが仕上げ研磨に数えるほど仕上がりに重要な働きをする工程です。
研磨法は中名倉、細名倉での”突き研ぎ”とは全く逆で刀身方向に”引く”という動作で行います。
決してシャクらずに反りに忠実に引くことに専念します。
この脇差の場合は白鞘製作で書いたように腰反りですから反りの強めなハバキ上近辺は特に短めに引かねばなりませんでした。
それとこの脇差は刃が比較的硬い出来ですので巣板砥という砥石で刃の中だけ先に細名倉の砥目を抜き、それから内曇砥に入りました。
内曇砥は”一日引いても錆は取れない”と言われるほど砥目が細かい砥石でして、これによって刃紋、地肌、働きなども完全に目に見える形となって現れてきますからまるで写真の現像のような趣もあります。
時間をかけてじっくり引くほど地刃の細かい働きが鮮明に現れてきますから本当に面白いし、楽しくなってくる作業です。
それと同時に、この内曇砥で充分に砥石が効いておりませんと次の仕上げ段階で作業が捗らないばかりか、仕上がりも拙いものになりますから神経を集中しなくてはならない工程でもあります。
「愛刀家の方々にもこの内曇の興味ある工程を分けて上げられたらどんなに良いだろう、きっともっと日本刀に興味を持てること請け合いです。」そんなことを考えながら作業してました。
刀身の指し裏の鎬地にやや目立つ鍛え疵、指し表の平地中央付近にフクレになりかけた箇所があり、それがこの脇差の欠点といいますか弱点ですね。
ただ、互目のたれの刃縁には働きも現れ、切っ先の帽子も沸え付いてしっかりしています。
これからの仕上げ研磨によっていかにこの脇差の長所が引き出せるか楽しみです。
しっかりした刃紋を見せる為に敢えて差込研磨で仕上げて素顔を見せるか、それとも上記の欠点を少しでもカバーするように後刃拾いで仕上げるか今迷ってます。
研磨ご依頼のお客様の中には差込研磨をご用命下さる方も少なくありませんし・・・。
どうぞ次回を御楽しみに・・・。
|
細名倉
|



研磨実演の脇差もいよいよ下地の終盤、細名倉砥まで来ました。
細名倉は実質的には下地の最終段階で、細名倉による研磨の良否が仕上がりまでかなり影響を及ぼしますから非常に重要な工程です。
この段階では当工房では必ず天然砥を使用します。
次の内曇砥の乗りの為、そして地刃の様子、下地の良否がこの天然細名倉によって決定し確認できるからです。
中名倉(改新砥)でも刀身方向にシャクリながら突く研磨法でしたがこの細名倉も同様に刀身方向に”タツを突く”研磨です。
しかし、中名倉よりも短い範囲を充分に効かせながら突いていきます。
裸電球にかざすと匂い口(刃紋)が煌びやかに浮かび刃中や刃縁の働きも見えてきます。
私個人的にこの天然細名倉のなんとも言えない輝きは仕上げ工程の地艶の輝きと同じ位好きです。
ですから自然と細名倉の研磨には気合が入ります。
話ははずれるかもしれませんが、砥石の工程は絶対前の研ぎ目を残してはいけませんね。
しかし、万一研ぎもらした場合、以前の砥目って一個置きに現れます。
つまり、備水の研ぎ残しは中名倉で、改正の研ぎ残しは細名倉でという具合です。
内曇砥では名倉以前の目を取り除くことはほとんど不可能ですから、この細名倉では
念には念をいれて、あらゆる角度と光線を当てて研ぎ目が残ってないかもチェックいたします。
幸い、この脇差の場合は研ぎ残しもありませんでしたし、肉置きなどもほぼ満足いく出来となりました。
天然の細名倉砥は現在全く採掘していないようで、砥石屋さんでも在庫があまりないようです。
時々砥石屋さんに行くと天然の細名倉砥石がガラスショーケースに入って飾られています。
私が数年前に購入した天然細名倉のサイズ(1.5キロ)ですらもう入手困難だというのですから異常事態です。
細名倉だけは天然が必要だと思いますが将来どうなるんでしょう。願わくは天然細名倉を上回る人造砥が一日も早く研究開発されることを期待します。
|
白鞘製作
|



ハバキの次は白鞘製作です。
日本刀の場合、錆身を研磨してもそれを収めておく入れ物、即ち、白鞘がありませんと保管もできませんし、危険ですから、白鞘は最低必要になります。
今回の材料は少し癖のある木でした。
部分的に木の繊維がかわり、順目と逆目が入れ替わり、鑿での中掻き、外の削りなどもいつもよりも時間がかかりました。
お客様に提供する鞘材の場合、もっと良い材料を使いますからそういう事もあまりないのですが、見た目の美しさだけでなく、作業の能率と言う面でも柾目の通った素直な材料が白鞘には必要だと改めて感じました。
さて、この脇差は腰反りですから中掻きなども均一な反りの刀に比べてやりずらい面があります。
刀身の輪郭通りに中掻きすると、反り具合の異なる箇所を刀身が通過する際必ず当たります。と言うか、抜き差しできません。
そのためスムーズな抜き差しが出来るように中掻きを行います。
薙刀のような先反りとは正反対の腰反りの中掻き。こんなところにも中掻きの慎重さが必要ですね。
外形は当工房の簡易白鞘と同じ小判型とし、木賊で磨き上げました。
今回の白鞘で一番の難所が目釘穴です。
なにしろナカゴの目釘穴を見ると小さいんです。
目釘穴は最後に開けますが、小さい穴ほど誤魔化しも融通も効きませんからより正確な位置に開けねばなりません。
いつも以上に錐を研いで準備しました。
良い白鞘とは何か、私はやはりスムーズに抜き差しができ、ガタや強く当る箇所がない丁寧に作られた白鞘だと思います。
そして、角口や鳩目もなどの装飾も結構ですが、白木だけのシンプルな白鞘が一番だと感じます。
また、装飾しなくても白木だけで美しい白鞘を研磨御依頼のお客様に御提供できるよう努力したいと考えてます。
ご質問やご感想などもお待ちしております。
|
ハバキと中名倉その2
|



中名倉(改新砥)で大筋違研ぎしてからハバキを作ってみました。
材質は純銀で祐乗ヤスリで仕上げた一重ハバキです。
ハバキの製作は地金を棟の部分を厚めに、平は薄めに延ばしてから折り曲げて、刃方に区金を入れてロウ付けする下地作り、ヤスリで整形し、磨き上げてから化粧ともいえる祐乗ヤスリを入れていきます。
この祐乗ヤスリは自家製のもので、一本一本ヤスリ目を突きながら玉も付けて行きます。
今回は総祐乗にしましたが写真映りから考えて腰祐乗のほうが良かったかなとも思いました。
当工房にハバキのない状態で来た御刀にはハバキ製作も行ってますが、やはり銀ハバキが一番お薦めです。
銀は銅のように緑青を吹くこともありませんし、銅に比べて軟らかいですから刀身にも優しいです。
製作する側からみても加工しやすくロウ付け、色上げなども銅ハバキよりも容易です。
本当に銀はハバキに最適な素材です。
さて、刀身の研磨ですが、前回と同じ改新砥で平地のタツ突きを行いました。
刀身方向、つまり縦の方向にシャクリながら研磨していきます。
これによって刃先から鎬まで5~6本の研ぎ目が付きます。
タツ突きによって大筋違の砥目が抜けると刃紋の状態や、鍛え肌なども見えてきました。
砥石を粗いものから細かいものに替え、次第に現れてくる刀の景色。
時間も労力もかなり使いますが同時に大変やりがいもあり楽しいものです。
この脇差は元来裸の赤錆でしたから鞘がありません。
ハバキができましたので次回は白鞘をお送りしたいと思います。
|
中名倉(改新砥)その1
|



錆身から研ぎ始めたこの脇差も中研ぎともいえる中名倉の段階まできました。
中名倉砥は元来、愛知県から採掘される天然砥石です。
この砥石も現在では人造の優秀な砥石が各メーカーから発売されておりますが、当工房では天然の中名倉砥にかわる砥石として”改新砥”という人造砥を使用しております。
この改新砥は効きがとにかく抜群で砥目を抜くだけなら備水の目も簡単に除去できるのではないか と思えるほどですし、二工程先の内曇砥にもすぐ入れるくらい肌理が細かい砥石です。
元々は外国の回転砥石ですが、砥石屋さんでは適当な大きさにカットされて発売されています。
難点は値段が他の人造名倉に比べて割高なこと、洗濯ソーダが使えないので真水で研がねばならないことでしょうか。
この改新砥で棟と鎬地をタツに突く、即ち刀身方向にシャクリながら改正砥の目を抜いていきます。
その後、平地を改正砥よりもさらに斜めの大筋違に研ぎながら改正砥では取りきれなかった微細なムラも除去していくわけです。
改新砥をかけると匂口や地肌の雰囲気も大方見えてきます。
中名倉の段階では特に平地に関しては今回の大筋違をしてから棟、鎬地同様にタツに突いていくという二段階を行います。
大筋違研ぎで改正までの砥目を完全に除去し、タツを突くことによって次の細名倉が効きやすいように整える働きがあるためです。
一工程ごとに固有の研ぎ方があり、そこには必ず必要とされる要素があるものです。
昔は天然砥だけでしたから現代よりさらに厳格に工程を重ねて行ったことと思いますが、優秀な人造砥が使用できる現代でもそれは大切なことだと感じます。
さてこの脇差も当初の状態から考えるとかなりシャープに姿も整ってきました。
通常は今回の段階を終えてハバキと白鞘を製作しますが、改新砥での平地のタツ突きを早くしてみたい衝動にもかられています。
タツを突いて取り合えずこの段階を終えるか、その前にハバキと白鞘の製作をするか、今日の段階では未定ですので次回をご期待ください。
|
改正名倉砥
|



改正名倉砥まで研ぎ進めてきました。
この改正名倉砥は人造砥を使いました。
前回の備水砥同様各メーカーからかなり優秀な人造砥が発売されており、特に改正砥に関しては天然砥石を凌ぐ製品が多数ありますから助かってます。
今回の砥石はその中でも整形には定評のある砥石を使ってみました。
まず、棟と鎬地は大筋違い(筋違いよりもさらに斜めの砥石目)で完全な平面になるように磨していきます。
次に平地を筋違い(斜めの砥石目)になるように研ぎます。
しかし、ただ筋違いに研ぐのではなく、改正砥からは”シャクリ研ぎ”という研ぎ方をします。
刀を砥石に当て、前に押しながら左右に擦り付けるように、揺らしながら研ぐ方法です。
この”シャクリ研ぎ”によって砥石が効いて備水の砥目が抜けていくというわけです。
ただし、シャクリを加えるということはそれだけ研磨効果があるわけですから、直刃ならまだしも乱刃の場合、うっかりすると刃の谷の部分が余計に減ってしまいますから大変注意が必要で、研ぎながらいつも気を遣ってます。
左右にシャクル研ぎ方ですから当然ながら砥石も左右に丸めた砥石を使います。
しかし、シャクってはならない横手際、ハバキのかかる錆際、切っ先内は平な砥石で行ってますし、 切っ先の刃先用には刃先を蹴らない為に特に前後に丸めた砥石も使用します。
改正名倉砥に限らず、同じ砥石でも研ぐ箇所に応じて形状の異なる砥石を用意しておくのもやはり必要なことだと思ってます。
さて、改正砥を終わると、本当にメリハリのある鋭い印象の刀身に見えてきます。
地刃の様子などもかなり見えてきました。
まだまだ先は長いですがじっくりと、そして楽しみながら工程を進めていきたいと思います。
次回は中名倉(改新砥)をお送りします。ご期待ください!
|
備水砥
|



前回の金剛砥に続き、備水砥という砥石での研磨です。
備水砥での工程は金剛砥よりも更に細かい箇所を正確に整形していきます。
そして同時に金剛砥の砥石目を完全に除去します。
棟と鎬地は筋違(斜めの砥石目)、そして平地は切り(真横の砥石目)に研ぎます。
これによって鎬地と棟は真平に、平地は理想的な肉置きになりました。
備水砥は人造の砥石が各メーカーから様々なものが発売されておりますし、当工房でも整形において
はかなりの種類を用意して使用しておりますが、最終調整は必ず天然備水砥で行っております。
天然の備水砥をかけると焼刃がよくわかりますし、瑞々しい独特な光沢は本当に美しいものです。
そして、不思議なことですが天然備水砥で研ぎますと、人造備水砥だけで工程を進めたものに比べ
仕上がりが一段と良くなるような気がします。
人造に比べ効きが劣るため、金筋や沸え、地景などの硬い組織が微妙に高く残る為でしょうか、天然砥の粒子に何か有効な成分があって、工程が進み、仕上がってからも作用するのでしょうか。
天然砥は不思議な魅力がありますね。
さて、この脇差、金剛砥の段階では、湾れ(のたれ)の刃紋に見えましたが、備水砥をかけますと湾れの山の中に互目が3個づつあることがわかりました。
そして、切っ先、つまり帽子は大変しっかりした刃です。
地金の肌はまだ正確にはわかりませんが比較的詰んでいるようです。
ただ裏の鎬地の一部に弱い地金の箇所が見られます。
今回の備水砥でほぼ整形という作業は完成し、このあとの改正名倉以降は砥目抜きがメインになります。
錆びた脇差がこの後の工程でどんな素顔を見せてくれるか、楽しみですね。
|
金剛砥
|



研磨の最初は一般的には備水砥から行うのですが、この脇差は刃毀れ、重ねムラ、歪みが酷いので金剛砥という砥石からの着手となりました。
まず、歪みや曲がりをタメ木で慎重に修正、その後、大きく出張ってる箇所だけを金剛砥で研いでいきます。
とにかくこの金剛砥は効きが抜群ですからいくら出張っている箇所とは言え色々な角度からこまめに確認しながら研磨をしないと必要以上に刀身を減らしてしまうことにもなりかねません。
古い御刀でも小鎬地の重ねが極端に薄くなってたり、刃区1寸の刃が凹んでいたりするものを良くみかけます。
多くは金剛砥などの粗い砥石で減らされたのではと思います。
大方の重ねムラや刃毀れを除去できましたら次は錆を取りながらの整形に入ります。
この脇差はペーパーや砥石で鎬筋は潰され、鎬地も丸く肉が付いてしまっています。
鎬地は真平に、そして平地は肉置きに注意しながら研磨していきます。
金剛砥ではあまり厳密に整形しようとせず、完璧な整形は次の備水砥に委ねますが、
切っ先の横手の位置、三つ角、刃角、小鎬の形状は定めておきます。(中央の写真)
金剛砥を一通りかけますと右の写真のように刃紋の形状が確認できます。
錆で良く分からなかった刃紋の形状がこの段階でわかりますから、嬉しい気持ちになってきます。
スタートしたばかりの錆脇差の研磨ですがご質問やご感想もたくさんお寄せください。
|
現状の錆身
|



御覧のような錆身の脇差です。
刃渡り54cm、反り1.3cmで”豊州高田住重行”と銘があります。
現状を仔細に観察するまでもなく「これは酷い!」と言いたくなるそんな脇差です。
所々に錆は噴出し、それを除去するためでしょうか、ペーパーや砥石で擦った痕跡があります。
特に砥石を当てられた箇所は鎬筋は潰れ丸くなり、地刃全体にムラだらけです。
刃筋は通らず、刃毀れも点在し、かなり傷められてしまっております。
棟から見ますと刀身が歪み、極端に出張っている箇所もあります。
幸いにも大きな疵はなさそうですし、刃紋も元から先までしっかり通っていますから日本刀としての実用的な価値は充分ありますし、美術刀剣としての要素ももしかして秘めているのでは?
当工房に送られてくる刀の多くがこのような状態です。
そして刀剣趣味を始められて最初に手にする刀、初めて研ぎに出そうという刀もこういう錆びた脇差が多いのではないでしょうか?
これから研磨をお考えのお客様のために少しでも参考になるよう頑張って書いて行こうと思います。
お問い合わせ
お問い合わせフォーム (←クリックお願いします)
所在地: 〒376-0013
群馬県桐生市広沢町2丁目3138-12
(直接お越しいただく場合は必ず前日までにご予約をお願いいたします)
TEL:0277-55-0871
(お問い合わせはメールまたはお問い合わせフォームからお願いいたします)
研師 柿沼進一
Facebookページも更新中です!